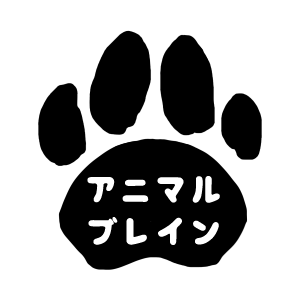捜索受付時間 9:00~21:00 / 捜索時間24時間
猫の活動リズムについて
猫の活動リズムは、人間の昼行性とも犬のような完全な昼型とも異なり、「薄明薄暮性(はくめいはくぼせい)」と呼ばれる特徴があります。これは、朝方と夕方の薄暗い時間帯にもっとも活発になる性質で、野生時代の狩猟習性が影響しています。以下に詳しく説明します。
基本的な活動サイクル
早朝(夜明け前後)
獲物となる小動物(ネズミや小鳥)が動き出す時間帯に合わせ、猫は最も活発になります。家庭の猫でもこの習性が残っており、飼い主を早朝に起こしに来たり、走り回ったりするのはこのためです。
日中(昼間)
多くの時間を睡眠やまどろみにあてます。猫は1日の半分以上(12〜16時間ほど)を寝て過ごしますが、これは「深い眠り」と「浅い眠り(レム睡眠に近い状態)」を短いサイクルで繰り返すためです。完全に無防備ではなく、物音や匂いに敏感に反応できる軽い睡眠が多いのも特徴です。
夕方(黄昏時)
もう一度活動が活発化します。走ったり、狩りごっこのような遊びをしたりするのもこの時間帯に多いです。飼い主と遊ぶなら夕方がもっとも適しています。
夜間(深夜〜明け方前)
個体差はありますが、多くの猫は再び活動し、遊んだり食べたりすることがあります。ただし完全な夜行性ではなく、深夜は休むことも多いです。
年齢による違い
子猫
好奇心旺盛で、活動時間が日中にも広がることが多いです。寝る時間は多いですが、短時間で起きて走り回ります。
成猫
最も典型的な「薄明薄暮性」のリズムが見られます。
老猫
活動時間は減り、より長く眠る傾向があります。特に日中に静かに過ごす時間が増えます。
飼育環境による影響
室内飼い
生活リズムが飼い主にある程度同調し、昼間に遊び、夜は一緒に眠るようになる場合があります。
外に出る猫
より野生に近いリズムを保ちやすく、夜明けや夕暮れに外に出たがります。
多頭飼い
一緒に暮らす猫同士で遊ぶ時間が増え、活動リズムも多少ずれることがあります。
健康とリズムの関係
活動リズムの急な変化は体調不良のサインになることがあります。例えば、普段活発な時間にまったく動かなくなる、逆に夜中に異常に騒ぐなどは、ストレスや病気の兆候かもしれません。
まとめ
猫は「薄明薄暮性」のリズムを持ち、早朝と夕方に最も活発になり、日中は長く眠ります。ただし、年齢・環境・個体差によってそのリズムは柔軟に変化します。飼い主は猫の自然なサイクルを理解し、特に活発になる時間帯に遊んであげることで、健康維持やストレス解消につながります。